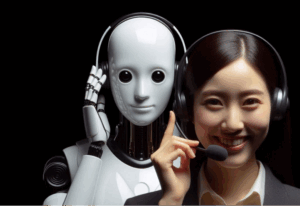近年、多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する中で、クラウドの利用が急速に拡大しています。クラウドを使えば、自社でサーバーを管理する手間が省け、コストを削減できるなどのメリットがあります。
しかし、その一方で、クラウドならではのセキュリティ上の課題も浮上しています。従来のオンプレミス環境とは異なり、クラウドでは、物理的なセキュリティ境界がなくなります。また、クラウドの柔軟性や拡張性を生かすために、社内の多くの部門がクラウドサービスを利用するようになりました。その結果、IT部門が把握していない「シャドーIT」が増加し、セキュリティ管理が複雑化しているのです。
こうした状況に対処するために、クラウドセキュリティ態勢管理(CSPM)という考え方が生まれました。本記事では、CSPMの概要、主要機能、導入手順、およびベストプラクティスについて解説します。
クラウドセキュリティ態勢管理(CSPM)とは
そもそもクラウドとは、インターネット上にあるサーバーやストレージ、アプリケーションなどのITリソースを、ネットワーク経由で利用するサービスのことです。会社のメールシステムやファイル共有サービスにクラウドを使っているところもあるでしょう。
クラウドを利用することで、自社でサーバーを管理する手間が省け、コストを削減できるなどのメリットがあります。しかし、クラウドを安全に使うには、適切なセキュリティ対策が必要不可欠です。
ここで登場するのが、クラウドセキュリティ態勢管理(CSPM)です。CSPMは、クラウド上のセキュリティ状況を常に監視し、問題があればすぐに見つけて改善するための仕組みです。
具体的には、CSPMは次のようなことを行います。
- クラウド上のすべてのシステムや設定を自動的にチェック
- セキュリティのルールに違反している部分の特定
- 見つけた問題を管理者に通知
- 問題を自動的に修正または、修正方法を提案
たとえば、クラウド上のサーバーにアクセス制限がかかっていなかったり、古いソフトウェアが使われていたりすると、CSPMが警告を出してくれます。こうすることで、セキュリティ上の弱点を早期に発見し、対処できるのです。
なぜクラウドセキュリティ態勢管理が重要なのか
皆さんの会社でも、クラウドの利用が増えているのではないでしょうか。実は、世界中の企業がどんどんクラウドを導入しています。しかし、クラウドを使えば使うほど、セキュリティのリスクも高くなります。
さらにサイバー攻撃は年々増えていて、手口も巧妙になっています。IBMの調査では、データ漏洩事故が1件起きると、平均して約4億2400万円の損害があるそうです。また、個人情報保護の法律が厳しくなっているため、クラウドを使う際のルールを守らないと、大きな罰金を払わなければならなくなるかもしれません。
このような状況の中で、CSPMはクラウドセキュリティを守るための重要な存在となっているのです。CSPMを使えば、クラウド上の危険な部分を見落とすことなく、素早く対応できます。
クラウドセキュリティ態勢管理(CSPM)の基本
ここでは、クラウドセキュリティ態勢管理の主要コンポーネントや従来のセキュリティ管理との違いなどを見ていきましょう。
クラウドセキュリティ態勢管理の主要コンポーネント
CSPMは、大きく分けて4つの役割を持っています。
- クラウド資産の可視化
CSPMは、クラウド上にあるすべてのシステムや設定を自動的に見つけ出し、リストを作ります。
- セキュリティポリシーの管理
CSPMは、クラウドを安全に使うためのルールをクラウド上のシステムに自動的に適用します。
- リスク評価とスコアリング
CSPMは、クラウド上の設定ミスや弱点を見つけ、危険度を評価します。
- コンプライアンス管理
CSPMは、クラウドがコンプライアンスを守れているかチェックし、報告書を作ります。
従来のセキュリティ管理との違い
従来、企業のシステムは自社のデータセンターで管理するのが一般的でした。これを「オンプレミス」と呼びます。オンプレミスでは、セキュリティ対策も企業が全部行います。
一方、クラウドでは、システムの管理を外部のクラウド事業者に任せます。クラウドでは、システムの追加や変更が簡単にできるため、セキュリティ状況も刻々と変化します。CSPMは、このような変化にリアルタイムで対応できるのです。
また、クラウドでは、セキュリティ対策の責任を、クラウド事業者と利用者である会社で分担します。これを「共有責任モデル」と呼びます。クラウドを使用するうえでは、どこまでが自社の責任で、どこからがクラウド事業者の責任なのか、明確に理解しなければいけません。
クラウド環境特有のセキュリティ課題
クラウドには、オンプレミスとは異なるセキュリティの課題があります。
- マルチクラウド環境の複雑性
企業で複数のクラウドを使うと、管理が複雑になります。それぞれのクラウドでセキュリティ設定を統一的に管理する必要があります。
- シャドーIT
従業員が許可なくクラウドサービスを使ってしまうことを、「シャドーIT」と呼びます。自社が管理していないクラウドサービスを使うと、セキュリティリスクが高まります。
- クラウドネイティブ技術のセキュリティ
コンテナやサーバーレスなど、クラウド特有の新しい技術があります。これらの技術には、従来とは違うセキュリティ上の注意点があります。
クラウドを安全に使うには、これらの特性をしっかり理解し、適切に管理することが重要です。
クラウドセキュリティ態勢管理(CSPM)の主要機能
それでは次に、CSPMの主要な機能について見ていきましょう。
可視性と資産管理
CSPMは、クラウド上のすべてのシステムや設定を自動的に見つけ出し、リストを作ります。これには、サーバー、ストレージ、ネットワーク、アプリケーションなどが含まれます。
また、CSPMはこれらのシステム同士の関係性を地図のように可視化します。これを「依存関係マッピング」と呼びます。システムの異常な動きやセキュリティ上の出来事があった場合、CSPMが警告を発してくれるのです。
コンプライアンスモニタリングと報告
CSPMは、GDPR(EU一般データ保護規則)、HIPAA(米国医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律)、PCI DSS(クレジットカード業界のセキュリティ基準)など、業界の標準やルールに沿っているかを常にチェックします。
また、自社独自のルールを設定して管理することも可能です。CSPMは、ルールに沿っているかどうかを示す報告書を自動的に作成します。これは、監査や証拠資料として使えます。
脆弱性評価と管理
CSPMは、クラウドの設定の弱点をスキャンし、セキュリティ上の隙間を見つけます。オープンソースツールや外部の製品と連携して、脆弱性スキャンを行うことも可能です。見つかった脆弱性は、危険度に応じて優先順位をつけ、修正計画を立てます。
設定ミスの検出と修正
クラウドの設定を間違えることが、セキュリティ事故の大きな原因の1つです。CSPMは、よくある設定ミスのパターンを把握しており、自動的に見つけ出します。
たとえば、アクセス権限を広く設定しすぎていたり、暗号化をしていなかったり、不要なポートを開けっぱなしにしていたりする場合などです。CSPMは、設定ミスを見つけると、修正方法を提案してくれます。
インシデント対応と自動修復
CSPMは、セキュリティ上の出来事を検知し、重大度に応じて分類します。インシデント対応の流れを自動化し、警告の通知、トラブルチケットの発行、担当者へのエスカレーションなどを効率的に行います。
さらに、事前に定義したルールに基づいて、自動的に修復アクションを実行し、インシデントの影響を最小限に抑えることも可能です。修復アクションの実行ログは、監査用に保存されます。
クラウドセキュリティ態勢管理(CSPM)の導入ステップ
それでは、CSPMを導入する際の具体的なステップを見ていきましょう。
1. クラウド環境の評価
CSPMを導入する前に、現在のクラウドの利用状況をしっかり把握することが大切です。どのクラウドサービスを使っているか、セキュリティ設定はどうなっているか、アプリケーションの構成はどうなっているかなどを文書にまとめます。そして、現在のセキュリティ対策で不足している部分を特定し、優先的に対処すべきリスクの高い領域を決めます。
2. セキュリティポリシーの策定
自社のセキュリティ目標に基づいて、クラウド環境のセキュリティポリシーを作ります。クラウドサービスの特徴に合わせてポリシーを設計し、関係部署の承認を得ましょう。ポリシーは定期的に見直し、更新するためのプロセスを決めておくことも肝要です。
3. 適切なCSPMツールの選択
自社ニーズに合ったCSPMツールを選ぶために、機能を比較します。主要なコンプライアンス要件に対応しているか、他のシステムとの統合ができるか、規模に合わせて拡張できるか、自動化の程度、ユーザーインターフェースの使いやすさなどを考慮します。
4. 導入計画の立案と実行
CSPMの導入は複雑になることもあるため、段階的に進めることをおすすめします。プロジェクトを複数のフェーズに分け、各フェーズの目標を設定します。また、必要なIT人材と予算を確保し、関係部署と連携する体制を作ります。
5. 継続的なモニタリングと改善
新しい脅威やルールに対応するために、CSPMは継続的に機能を強化していく必要があります。定期的にレビューを行い、改善点を見つけましょう。同時にCSPMツールのアップデートやセキュリティポリシーの見直しも重要です。
クラウドセキュリティ態勢管理(CSPM)のベストプラクティス
CSPMを効果的に運用するには、いくつかのベストプラクティスがあります。ここでは、その主なものを見ていきましょう。
1. 自動化を活用する
CSPMの大きな目的の1つは、セキュリティ運用を自動化することです。設定ミスの検出、修復、インシデント対応など、できるだけ自動化すべきタスクを見極めます。自動化することで、人的ミスを防ぎ、対応時間を短縮できます。
2. 従業員教育とトレーニング
クラウドのセキュリティを確保するには、従業員の意識向上が欠かせません。クラウドセキュリティの基礎知識、CSPMツールの使い方、セキュリティのベストプラクティスなどのトレーニングプログラムを実施します。
たとえば、CSPMツールを導入しても、従業員が容易に推測できるパスワードを使いまわししては、サイバー攻撃のリスクが高まります。
クラウドセキュリティの確保には、技術的な対策だけでなく、従業員の意識向上も不可欠です。
3. サードパーティリスクの管理
クラウドサービス事業者や外部のアプリケーションのセキュリティ評価を行います。信頼できるベンダーを選び、定期的にセキュリティ監査を実施します。外部の業者と契約する際は、セキュリティ要件を明確に定義したベンダー管理ポリシーを作ります。
4. インシデント対応計画の定期的な更新
クラウド環境では、従来のオンプレミス環境とは異なるタイプのセキュリティインシデントが発生する可能性があります。たとえば、大量のトラフィックを送りサービスを使用停止にするDoS攻撃、セキュリティルール違反による設定ミス、従業員が誤って機密情報を公開するなどです。
これらのシナリオに基づいて、インシデント対応手順を文書化します。CSPMツールで検知されたインシデントに対して、いつ、誰が、どのように対応するかを明確にしましょう。
まとめ
デジタルトランスフォーメーションが加速する中、クラウドの戦略的活用は企業の競争力を大きく左右します。しかし、そのメリットを享受するためには、クラウドのセキュリティを確実なものとしなければなりません。CSPMは、そのための強力な武器となるでしょう。
クラウドセキュリティを考える上で、見落としがちながらも重要な領域がダークウェブ監視です。ダークウェブとは、一般的な検索エンジンではアクセスできない、匿名性の高いウェブサイトの集合体を指します。サイバー犯罪者たちは、ダークウェブ上で情報を売買し、攻撃を計画しています。
企業にとって、ダークウェブ上で自社の機密情報や顧客データが取引されていないかを監視することは極めて重要です。情報漏洩は、深刻な経済的損失やブランド毀損、信頼の墜落につながります。早期発見が被害を最小限に抑える鍵となります。
しかし、ダークウェブ監視は容易ではありません。ダークウェブへのアクセスには特別なソフトウェアが必要で、大量の情報から関連する脅威を見つけ出すのは困難を極めます。そこで重要な役割を果たすのが、ダークウェブ監視サービスです。
当社では、先進的なダークウェブ監視サービス「ZERO DARKWEB」を提供しています。本サービスは、ダークウェブ上の膨大な情報を自動的に収集・分析し、企業に関連する脅威情報を検出します。自社の漏洩情報が見つかれば、即座にアラートを発します。
弊社のダークウェブ監視サービス「ZERO DARKEWB」に興味をお持ちの方は、ぜひ無料デモをお申し込みください。実際に自社のサービス画面をご覧いただき、どのようにダークウェブの脅威からビジネスを守れるかを実感していただけるはずです。
弊社はダークウェブ調査(無料)を実施しています。
こちらからお申し込みください。