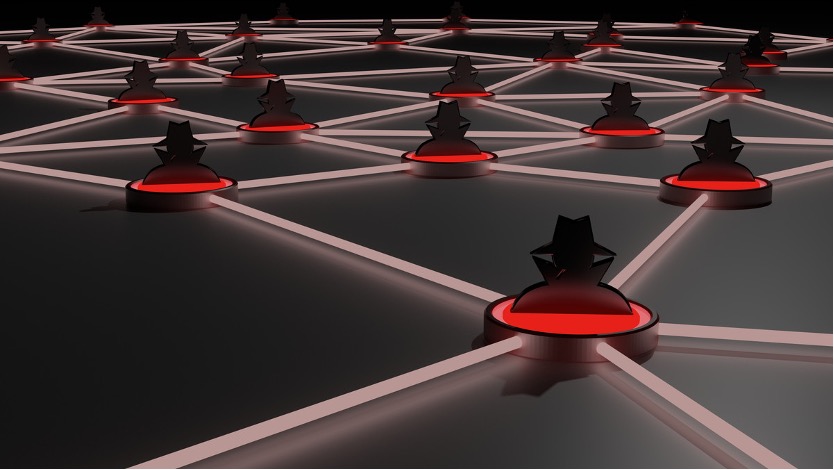
製造業では近年、急速にデジタル化が進んでいます。
IoTによる生産設備の接続、遠隔監視システムの導入、リモート保守の常態化など、現場はより効率的で柔軟な体制へと移行しつつあります。しかしその一方で、工場のネットワークが外部とつながる機会が増えるほど、サイバー攻撃にさらされるリスクも確実に高まっています。
特に中小工場では、セキュリティ専任者が不在であったり、運用ルールが曖昧なまま放置されていたりと、攻撃者にとって狙いやすく、効率のよい標的になっているのが現実です。自社は関係ない、大企業が狙われるものだ、そうした油断が、深刻な被害につながる可能性もあります。
本記事では、なぜ今、製造業の工場がサイバー攻撃の対象となっているのかを明らかにし、代表的な攻撃手口やその被害、さらに中小企業でも実践可能な具体的なセキュリティ対策について解説します。
なぜ今、製造業・工場のセキュリティが狙われているのか?
まずは、製造業と工場がサイバー攻撃の標的になっている2つの理由を整理します。
工場のDX化が進む一方、セキュリティは追いついていない
製造現場では現在、デジタル化の波が急速に広がっています。
機械設備のIoT化や遠隔操作による保守・監視、リモートワーク環境の導入により、従来は閉じられていた工場のネットワークが外部と接続されるようになりました。この変化は、生産効率やトラブル対応力の向上といった多くのメリットをもたらしています。
一方で、多くの現場ではセキュリティ対策が追いついていないのが実情です。たとえば、社内ネットワークと制御システムの境界が不明確なまま運用されていたり、リモートアクセスの仕組みを急遽導入したりしたことで、パスワード管理や通信の暗号化が不十分なケースが見受けられます。
さらに、中小規模の工場では専任のIT担当者が不在であることも珍しくありません。
日々の業務に追われる中で、サイバーリスクへの理解や対策は後回しになりがちです。その結果、新たに生まれた脅威に対して無防備な状態で接続されている工場も少なくなく、攻撃者にとって格好の標的となっています。
中小工場は狙いやすく、割がいいターゲット
サイバー攻撃者にとって最も狙いやすいのは、「防御が甘く、かつ価値のある情報を持つ組織」です。中小規模の製造業は、まさにその条件に合致します。
VPNやリモートデスクトップ(RDP)、NASといった機器の設定ミスや、初期設定のまま放置されている例は少なくなく、外部からの侵入が容易なケースも散見されます。
加えて、こうした企業ではセキュリティ教育が不十分であったり、専用の防御ソリューションを導入する予算が限られていたりと、全体として防御体制が脆弱です。それにもかかわらず、設計図や製造ノウハウといった機密性の高い情報を保有しており、攻撃者からすれば「少ない労力で大きな成果」が期待できる、いわば効率のよい標的となってしまいます。
さらに、工場という業態の特性上、一度操業が停止すれば多大な損失が発生します。
仮にランサムウェアによってシステムを人質に取られた場合、復旧を急ぐあまり、一定の金額であれば支払う選択をする傾向も見られます。攻撃者はその心理を熟知しており、「止まれば困る企業」は交渉の余地があると見なされ、より狙われやすくなるのです。
工場セキュリティとは? ITセキュリティとの違い
工場におけるセキュリティは、情報システム部門が担うITセキュリティとは目的は似ていても、性質や優先順位が大きく異なります。守る対象や脅威の種類、求められる条件が違うため、これを理解しないままでは十分な対策は実現できません。
ITセキュリティでは「機密性」「完全性」「可用性」の3要素のバランスが重視されます。顧客情報の保護や業務の継続性が中心です。一方、工場セキュリティの中心となるOT(Operational Technology)セキュリティでは「可用性」が最優先。工場が止まれば、生産や出荷に直結する損失が発生するためです。
また、IT機器と異なり、工場設備は10年以上使われることも多く、古いOSやソフトがそのまま使われている例も少なくありません。アップデートによる不具合を避けるため、更新が敬遠され、脆弱性が放置されるケースもあります。
OTではリアルタイム制御が必須であり、ウイルススキャンやファイアウォールが動作遅延を招くため、一般的なIT対策が適用しづらい現実もあります。
こうした違いがある一方で、ITとOTはますます接続されるようになり、IT由来の攻撃が工場の制御系に影響を与える例も増えています。もはや両者を分けて考えること自体がリスクになりつつあります。
工場を狙う主なサイバー攻撃とその被害
ここでは、向上を狙う主なサイバー攻撃とそれがもたらす被害について見ていきましょう。
ランサムウェア攻撃
近年、製造業におけるサイバー被害で最も多く報告されているのが、ランサムウェアによる攻撃です。
これは、生産管理システムや設計データを暗号化し、その復号と引き換えに「身代金(Ransom)」を要求する手口であり、「止まることが許されない」工場を狙い撃ちにしています。
たとえば、攻撃者が生産管理システムに侵入し、数百GBに及ぶ図面データや生産スケジュールを暗号化すれば、工場は部品の手配もラインの稼働もできなくなるでしょう。復旧の見通しが立たない中で、やむを得ず仮復旧やデータの再構築を試みても、最終的に身代金を支払わなければ業務を再開できないという状況に追い込まれることもあります。
さらに深刻なのは、身代金を支払っても復号されないケースがあることです。
セキュリティ業界では、交渉の末に多額のビットコインを支払ったにもかかわらず、復号キーが送られてこなかった事例が複数報告されています。つまり、被害に遭った時点で業務停止と金銭的損失の両方を抱える、最悪の事態が待ち受けているのです。
サプライチェーン攻撃
サプライチェーン攻撃とは、自社ではなく取引先を経由して侵入される手口です。たとえば、大手製造業A社と、その一次下請けである中小企業B社がEDIやVPNで接続している場合、攻撃者はまずB社の脆弱な箇所を突いて侵入し、そこを足がかりにA社のシステムへ攻撃を広げます。
この攻撃の厄介な点は、自社が直接攻撃されなくても、被害の原因と見なされる可能性があることです。B社にとっては、取引先にマルウェアを拡散した加害者として、損害賠償請求や契約停止といった重大な責任を問われるリスクがあります。
VPNの設定ミスやアカウント共有など、日常的な運用の甘さが、大きな被害を引き起こすのがサプライチェーン攻撃の恐ろしさです。
フィッシング・BEC詐欺
フィッシング詐欺は、攻撃者が正規の取引先や金融機関を装ってメールを送り、受信者を偽サイトに誘導したり、添付ファイルを開かせたりする手口です。
さらに近年では、BEC(Business Email Compromise)、いわゆるビジネスメール詐欺が急増しています。これは、経理や購買担当者に対し、取引先や上司を装って「振込先が変更された」と伝えるメールを送りつけ、送金を誘導するというものです。たった一度の誤認で、数百万〜数千万円の資金が攻撃者の口座へ送られてしまいます。
特に製造業では、資材発注や外注費の支払いが日常的に発生するため、「この請求は本物か?」と確認する余裕がないケースも少なくありません。その結果、日本語の文面が自然であれば、疑わずにそのまま処理してしまう例が後を絶ちません。
情報漏洩とダークウェブでの拡散
最後に見逃せないのが、情報漏洩とそれに伴うダークウェブでの拡散です。攻撃者が一度社内ネットワークに侵入すれば、設計データや顧客リスト、ログイン情報など、さまざまな機密情報が盗まれる可能性があります。そして、それらの情報は暗号資産と引き換えに、ダークウェブ上で売買されることになります。
問題は、流出してもすぐには気づけない点です。ある日突然、取引先から貴社の設計図が外部に出回っていると連絡を受け、そこで初めて漏洩に気づくケースも珍しくありません。さらに、流出した情報が競合他社に渡れば、価格競争の激化や模倣品の流通といった、二次・三次被害を招くおそれもあります。
一度流出した情報は、完全な回収が不可能です。インターネット上のどこかにコピーが残り続け、永続的なリスクとして組織に影響を与えます。つまり、漏洩に気づけなかったことが、後の信頼失墜へと直結するのです。
工場セキュリティの三本柱:人・運用・技術
ここでは、工場セキュリティの3つの柱について見ていきましょう。
People(人)
どれほど優れた技術を導入しても、それを使うのは人です。つまり、セキュリティの最前線に立つのは、現場で働く従業員一人ひとりにほかなりません。にもかかわらず、製造現場ではセキュリティはIT部門の担当として切り離され、現場の理解や意識が十分に浸透していないケースが少なくありません。
特に中小工場では、経営者自身が「うちは狙われない」とリスクを過小評価していることもあります。そのような環境では、現場任せにされた従業員も本格的に対策へ取り組むのは難しいでしょう。だからこそ、経営者が先頭に立ち、セキュリティは全員で取り組むべき課題との方針を明確にし、組織全体に共有することが重要です。
加えて、現場レベルでの声がけや啓発活動も欠かせません。たとえば、USBの使用ルールを明示したり、定期的な注意喚起を行ったりといった日常的な取り組みが、セキュリティ意識の定着につながります。
Process(運用)
セキュリティ対策は、技術や人材だけで完結するものではありません。重要なのは、それらをどのように運用するかという仕組みそのものです。
セキュリティポリシーの整備、定期的な訓練、インシデント対応体制の構築など、ルールの策定と継続的な運用がなければ、対策は日常業務の中で形骸化してしまいます。
たとえば、パスワード管理や外部メディアの扱い、VPNの使用といった基本的なルールについて、文書化されたポリシーがなければ、判断が各担当者に委ねられ、統一した運用は困難になるでしょう。
まずは現場の実態に合ったルールを明文化し、全員が理解し共有できる状態をつくることが出発点です。
また、セキュリティインシデントは「いつか起こるもの」として備える姿勢が欠かせません。年に一度でもよいので、訓練や机上シミュレーションを通じて、「業務端末がランサムウェアに感染したら?」「取引先から口座変更の連絡があったら?」といった具体的なシナリオを検討することが効果的です。
こうした訓練を積むことで、現実的な対応力が育まれ、緊急時にも慌てずに対処できる組織づくりにつながります。
Technology(技術)
当然ながら技術的な対策も欠かせません。むしろ、攻撃を物理的に防ぐには、適切な技術の選定とその運用が前提となります。特に工場においては、ITとOTを明確に区切る「ゾーン分離」の考え方が重要です。
たとえば、インターネットに接続するPCと設備制御用端末を物理的・論理的に分離することで、仮にIT側が侵害されても、OTへの波及を防げます。
また、アクセス権限の最小化も基本です。
管理者権限は特定のユーザーに限定し、他のアカウントには必要最小限の操作のみを許可することで、万が一IDが盗まれても被害の範囲を抑えられます。
加えて、定期的なバックアップの仕組みも不可欠です。特に設計データや生産管理ファイルといった基幹データは、外部ストレージやクラウドへの自動バックアップを行い、緊急時には迅速に復旧できる体制を整えておく必要があります。
これらの技術的対策こそが、攻撃を「防ぎ、検知し、回復する」ための土台となります。
予算が限られた中小工場でも必ず行うべきセキュリティ対策
ここでは、予算が限られた工場でも最低限実施しておくべきセキュリティ対策をご紹介します。
二段階認証(MFA)の導入
限られた予算で実施できる、効果的なセキュリティ対策の一つが二段階認証(MFA)です。これは、パスワードに加えてスマートフォンなどの別要素を使ってログインを行う仕組みで、たとえパスワードが漏洩しても、不正アクセスを防ぐことができます。
たとえば、メールアカウントやNAS、クラウドサービスなど、工場業務で使用する各種アカウントにMFAを導入することで、侵入リスクを大幅に低減できます。
特に注目すべきは、その導入コストの低さです。
多くのクラウドサービスではMFAが標準機能として提供されており、物理トークンを用意しなくても、スマートフォン1台で対応可能です。高価なシステムや専門知識を必要とせず、すぐに実行できる対策として有効です。
社員へのフィッシング訓練
技術的な防御と並んで重要なのが、従業員の判断力を高めることです。フィッシングメールは年々巧妙化しており、件名や文面、差出人情報まで本物そっくりに偽装されているケースもあります。そのため、実際にメールを受け取る社員自身が、攻撃かどうかを即座に見抜く力を持つことが、被害の抑止につながります。
現実的な手法としては、月に1回程度の模擬フィッシング訓練が効果的です。実際の業務メールに似せた偽メールを社内に送信し、クリックした社員にフィードバックを行うことで、注意力を高めることができます。
こうした訓練を継続することで、社員は怪しい兆候に敏感になり、自然とリスク察知の感覚が身につきます。訓練用サービスも比較的安価で提供されており、限られた予算でも導入しやすい点が魅力です。
古いNAS・機器の外部公開を即時停止
多くの中小工場で見落とされがちなのが、古いNASやネットワーク機器がインターネット上に公開されたまま放置されているケースです。
攻撃者は世界中を自動でスキャンし、こうした脆弱な機器を探し続けています。古いNAS、プリンター、監視カメラなどは、セキュリティパッチが提供されていなかったり、初期設定のまま運用されていたりする例が少なくありません。
たとえば、管理画面に「admin / 1234」でログインできるような状態は、まさに「侵入してください」と言っているのと同じです。
まずは外部からのアクセスを遮断し、必要があれば社内ネットワーク内だけで使用できるよう設定を見直すだけでも、攻撃対象となるリスクは大幅に低減します。
メールでの口座変更連絡は電話で確認
ビジネスメール詐欺(BEC)を防ぐうえで、最もシンプルかつ効果的な対策が電話による確認です。
取引先を装ったメールで「振込先が変更された」と指示され、そのまま送金してしまう被害が後を絶ちません。メールのドメインや文面が精巧に偽装されている場合、目視による判別は困難です。
そのため、振込先や金額、入金日など、金銭に関わる情報の変更をメールで受け取った際は、必ず電話で確認を取るというルールを社内で徹底しましょう。実際に相手の声を聞き、所属や依頼内容を確認すれば、メールだけでは防げないリスクを確実にブロックできます。
コストや手間がほとんどかからない、今すぐ実施可能な対策です。
ダークウェブ監視で漏洩に気づける体制構築
セキュリティ対策は攻撃されないことに目が向きがちですが、漏洩に早く気づくことも同じくらい重要です。ダークウェブでは、盗まれたメールアドレス、ログインID、パスワードなどの情報が日々売買されており、それに気づかず使い続けている企業は、次なる攻撃の標的となります。
このため、自社の情報が流出していないかを継続的に監視する体制を整えることが有効です。現在では低価格のSaaS型のダークウェブ監視サービスも登場しており、専門知識がなくても導入可能です。
漏洩が確認された際に迅速なパスワード変更や関係者への通知が可能となり、被害の拡大を防げます。
まとめ:中小工場でも「やれる対策」から始めよう
サイバー攻撃は、今やあらゆる工場にとって無視できない脅威です。大企業だけが狙われるという時代は終わり、防御が手薄な中小工場こそ、攻撃者にとって格好の標的となっています。
とはいえ、完璧を目指す必要はありません。限られた予算でも、操業の継続、ヒューマンエラーの防止、金銭の流出防止に集中することで、大きな被害は避けられます。具体的には、入口を塞ぐ、判断力を育てる、金銭リスクを遮断するという三つのポイントを徹底することが重要です。
加えて、情報漏洩に早く気づく仕組みを持つことも欠かせません。特にダークウェブでは、企業のIDやパスワードが売買されており、放置すれば二次被害につながります。いち早く流出を検知し、対応する体制が求められています。
弊社は専門知識不要で使えるSaaS型のダークウェブ監視サービスを提供しています。自社の情報が不安な方、何から始めればよいか迷っている方は、まず無料デモでその効果をご体感ください。



