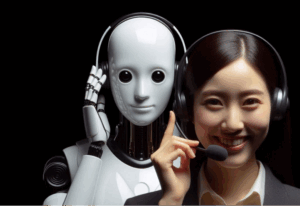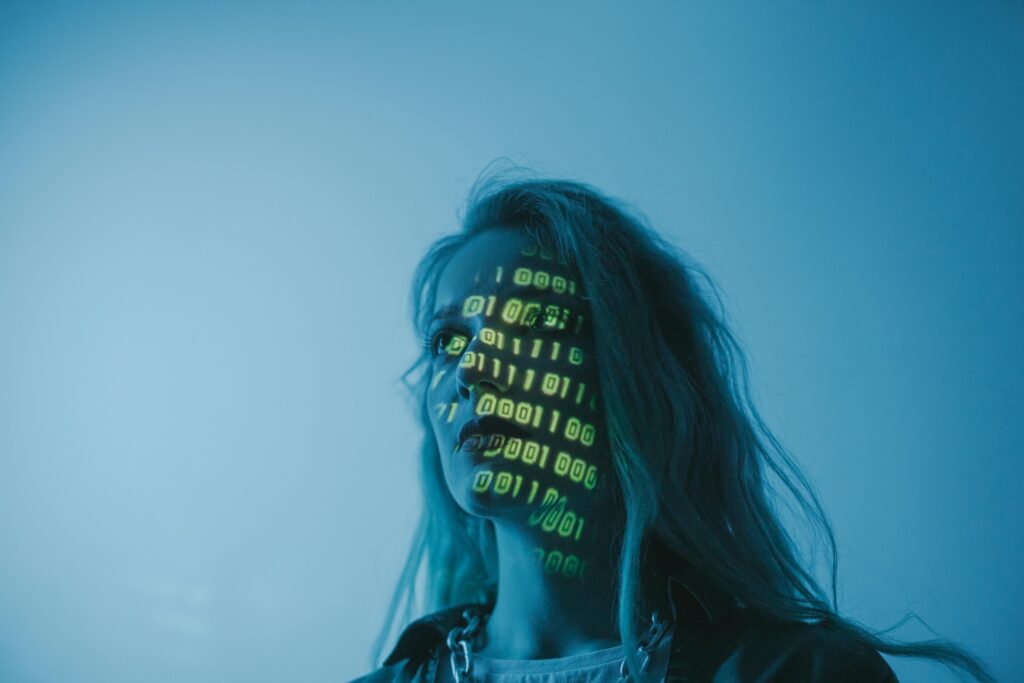
不正アクセス、ウイルス感染、情報漏洩。
今やこうしたサイバーリスクは、大企業だけでなく中小企業にも等しく降りかかる時代です。特に、IT専任者が不在だったり、複数の業務を兼任したりている現場では、セキュリティ対策にまで手が回らないという声も少なくありません。
そこで注目されているのが、ファイアウォールやウイルス対策などをひとつにまとめて運用できるUTM(統合脅威管理)です。専門知識がなくても扱いやすく、多層的な防御を実現できるUTMは、まさに中小企業の守りを自動化する強い味方といえるでしょう。
本記事では、UTMの基本や他セキュリティ対策との違い、導入のメリット、製品の選び方までをわかりやすく整理しながら、中小企業がなぜ今この対策を進めるべきなのかを具体的に解説していきます。
中小企業にこそおすすめのUTMとは
UTM(Unified Threat Management:統合脅威管理)とは、ファイアウォールやアンチウイルス、侵入防御など、従来は別々に導入・管理されていたセキュリティ機能を、ひとつの機器またはクラウドサービスにまとめたものです。
従来、ファイアウォール、アンチウイルス、侵入検知システム(IDS)、メールフィルタリングなどを個別に導入・運用されていました。しかし、それぞれのツールに専門知識が必要なうえ、複数の管理画面を行き来して設定や監視を行うのは、小規模なチームにとって大きな負担です。UTMはそれらの機能を1つにまとめ、単一の管理画面で一括操作できるようにすることで、そうした煩雑さを解消します。
UTMは、限られた人材・時間・予算で効率よくセキュリティ対策を行いたい中小企業にとって、相性の良い仕組みです。
UTMとファイアウォール・ウイルス対策ソフトとの違い
UTMを検討する際、多くの方が疑問に感じるのが「既にファイアウォールやウイルス対策ソフトを使っているけど、それでは足りないのか?」という点です。実際、これらのツールはいずれもセキュリティの基本として広く導入されています。しかし、UTMとは役割や範囲が大きく異なります。ここでは、それぞれの違いについて順に解説します。
ファイアウォールとの違い
ファイアウォールは、社内ネットワークと外部ネットワークの間に立ち、不正なアクセスを遮断する役割を担うセキュリティ機器です。IPアドレスやポート番号などを基準に、どの通信を許可し、どれを遮断するかを設定できるため、ネットワークの出入り口を守る門番のような存在です。
一方で、ファイアウォール単体では、ウイルス感染やフィッシングサイトへのアクセス、業務と無関係なWeb利用の制御など、より広範な脅威への対処には限界があります。たとえば、ファイアウォールでは許可されている通信であっても、その中に不正なファイルが含まれている可能性までは判断できません。
UTMは、こうしたファイアウォールの基本機能に加えて、アンチウイルス、Webフィルタリング、IDS/IPS(侵入検知・防御)など、複数の防御機能を組み合わせて提供します。そのため、外部の悪意あるサイトへのアクセスを自動でブロックしたり、感染した端末からの不審な通信を検知・遮断したりすることも可能です。
つまり、ファイアウォールがネットワークの入り口を見張るのに対し、UTMはその入り口を含む建物全体を見回り、複数の視点から異常を検知する警備員のような存在です。
ウイルス対策ソフトとの違い
ウイルス対策ソフトは、主にPCやサーバー端末内で動作し、マルウェアやスパイウェア、ランサムウェアといった悪意あるプログラムの侵入・実行を検出してブロックする役割を担います。
多くの企業では、社員が使用するパソコンに標準でインストールされているため、身近なセキュリティ対策として定着しています。
しかし、ウイルス対策ソフトが保護するのは、基本的にその端末の中だけです。ネットワーク全体の挙動や外部からのアクセス、不正な通信の検知といった役割は担いません。また、すべての端末に確実にインストールされていて、常に最新の状態でなければ、その効果も限定的です。
UTMは、こうした端末ベースの対策とは異なり、ネットワークの出入り口に設置して社内全体の通信を監視・制御します。つまり、社内のどの端末が、どこにアクセスし、何をやり取りしているかを把握できるため、異常な動きを早期に発見することが可能です。
ウイルス対策ソフトが点(端末)を守るのに対し、UTMは線(通信)や面(ネットワーク全体)を守る役割を担います。
中小企業向けUTMの種類
UTMと一口に言っても、その提供形態にはいくつかの種類があります。実際の運用環境や管理体制、コスト感によって最適な選択肢は異なります。
ここでは、中小企業でも導入されることの多い3つのUTMタイプについて、それぞれの特徴や向いている企業像を解説していきます。
オンプレミス型UTM
オンプレミス型UTMとは、自社内に設置する専用機器を通じてネットワークを保護する方式です。
ルーターやスイッチと同様、社内LANの出入り口に物理的なUTM装置を接続し、そこから全社の通信を監視・制御する仕組みです。特に社内にサーバーを置いている企業や、ネットワーク構成が複雑な場合に適しています。
たとえば、自社オフィス内で社内システムやファイルサーバーを運用している製造業の企業では、社内ネットワークの内部から外部、そして外部からのアクセスをすべて可視化・制御できるこの方式が効果的です。また、クラウド利用が少なく、通信が主に社内完結している環境では、オンプレミス型が安定して機能します。
メリットとしては、インターネットに依存せずに高度な制御ができる点と、物理的に設置されているためネットワーク障害時にも影響を最小限に抑えられる点が挙げられます。一方で、機器の保守・更新や設定作業にはある程度のITスキルが必要であり、専任の管理者がいない中小企業では、外部業者のサポートが前提になるケースもあります。
クラウド型UTM
クラウド型UTMは、物理的な装置を設置するのではなく、インターネット経由で提供されるUTMサービスを利用する方式です。
専用機器の導入や保守が不要で、インターネット回線に接続するだけで多層的なセキュリティ機能を利用できるため、特にITリソースが限られた中小企業にとって導入のハードルが低いのが大きな特徴です。
メリットとしては、導入が迅速で、初期費用を抑えやすい点、そして常に最新のセキュリティ機能を自動で適用してくれる点が挙げられます。一方で、通信経路のすべてをクラウド側に依存するため、インターネット接続が不安定な環境ではパフォーマンスに影響が出ることもあります。
ハードウェアアプライアンス型UTM
ハードウェアアプライアンス型UTMは、UTM機能があらかじめ組み込まれた専用の物理機器を導入するタイプで、多くの中小企業で採用されている主流の方式です。見た目はルーターやNASと似た箱型の装置で、LANとWANの間に設置することで、社内外の通信をリアルタイムで監視・制御します。
このタイプの特長は、設定が比較的簡単で、ベンダーや販売代理店が提供するテンプレート設定に従うだけで基本機能がすぐに使える点です。たとえば、ITに詳しくない経営者が「最低限のセキュリティは整えておきたい」と考えた場合でも、外部ベンダーが初期設定から保守まで対応してくれるため、安心して任せられます。
また、多くのハードウェアUTM製品には、ダッシュボード形式の管理画面が用意されており、どの端末がどこにアクセスしているか、ウイルスや不正通信が検知されたかなどを一目で確認できます。複雑な設定知識がなくても、セキュリティ状況を把握しやすいのがメリットです。
ただし、導入時に一定の初期費用が発生する点や、機器の物理的な故障リスク、年単位の保守契約が必要なケースもある点には注意が必要です。とはいえ、コストと使いやすさ、セキュリティ効果のバランスが取れていることから、現実的な選択肢として多くの中小企業が導入しています。
UTMの主な機能
UTMは、複数のセキュリティ機能を1つに統合した製品ですが、実際にどのような機能が搭載されているのかを具体的に理解しておくことは、製品選定や運用において重要です。
ここでは、代表的なUTMの構成要素である6つの機能を見ていきましょう。
ファイアウォール機能
ファイアウォール機能は、UTMの基本機能のひとつであり、社内ネットワークと外部インターネットとの間に立って、許可された通信だけを通す交通整理の役割を果たします。不正アクセスや不審なポートスキャンなど、外部からの攻撃的な通信をブロックすることができます。
従来の独立型ファイアウォールと同様に、IPアドレス、ポート番号、通信プロトコルなどに基づいて通信の可否を判断できますが、UTM内蔵型のファイアウォールは、他のセキュリティ機能と連携して脅威を多面的に評価できる点が大きな違いです。
アンチウイルス・マルウェア対策
アンチウイルス・マルウェア対策は、UTMの中でも特に重要な機能の一つです。これは、社内ネットワークを流れるデータの中に、ウイルスやスパイウェア、ランサムウェアなどの悪意あるコードが含まれていないかを検知し、必要に応じて自動でブロックするものです。
従来は、社員一人ひとりのPCにウイルス対策ソフトをインストールして個別に管理していた企業が多いかもしれません。しかしこの方法では、更新の抜け漏れや誤設定があると、そこから被害が広がってしまうリスクがあります。UTMでは、ネットワークの出入り口で全ての通信を監視するため、各端末に依存せず、組織全体をまとめて防御することが可能になります。
Webフィルタリング
Webフィルタリングは、社内の端末からインターネット上の不適切・危険なサイトへのアクセスを制限する機能です。これは単に業務に関係のないサイトへのアクセスをブロックするだけでなく、マルウェア感染やフィッシング詐欺の被害を未然に防ぐ目的でも活用されます。
具体的には、社員が業務中に何気なく開いたサイトが、実は不正なスクリプトを仕込んだ攻撃用のサイトだった場合、Webフィルタリング機能があれば、そのURLを即座にブロックし、感染のリスクを抑えられます。リスクレベルごとにカテゴリ分けされたデータベースに基づいて、危険なURLやジャンルを自動的に検知・制御できる仕組みです。
また、就業中の業務効率や生産性という観点からも、SNSや動画サイトなどへのアクセス制限は有効です。UTMによっては曜日や時間帯、ユーザーグループごとのポリシーを柔軟に設定できるため、たとえば「営業部は昼休み中だけSNSアクセス可」といったルールも簡単に構築できます。
IDS/IPS(侵入検知・防御)
IDS(Intrusion Detection System)は、不正アクセスや異常な通信を検知する仕組みであり、IPS(Intrusion Prevention System)は、それらを検知したうえで自動的に遮断する防御機能です。どちらも「すでに通過してしまった通信」に対してセーフティネットのように機能し、UTMにおいては両者が統合された形で搭載されていることが一般的です。
たとえば、外部から社内サーバーに向けて繰り返しパスワードを試すようなブルートフォース攻撃や脆弱性を突くような通信があった場合、IDSはその異常を検出し、IPSはその通信を遮断して被害の拡大を防ぎます。
これにより、ファイアウォールだけでは防げない内部に入り込まれた後の異常行動にも対応できるのです。
VPN(リモートアクセス)
VPN(Virtual Private Network)は、インターネット上に仮想の専用回線を構築し、安全にデータをやり取りするための仕組みです。UTMにはこのVPN機能が標準で備わっていることが多く、リモートワークや外出先から社内システムへ安全にアクセスしたい中小企業にとっては心強い機能です。
たとえば、営業担当者が出張先のWi-Fiから社内のファイルサーバーにアクセスする場合、その通信は傍受されるリスクがあります。しかし、VPNを経由すれば、通信は暗号化され、第三者に情報を読み取られる心配がなくなります。
加えて、UTMのVPN機能は、社内のネットワークと一貫したセキュリティポリシーのもとで通信を管理できるため、個別のPC設定に頼らずとも安全性が保たれます。
アプリケーション制御
アプリケーション制御とは、社内ネットワーク上で利用されているソフトウェアやWebサービスごとの通信を識別し、使用の可否や制限を細かく設定できる機能です。
従来のファイアウォールでは通信元のIPアドレスやポート番号を基に制御していましたが、アプリケーション制御では、それだけでは判断できない「何のサービスか?」を正確に識別できる点が特長です。
一例をあげると、YouTubeやLINE、DropboxなどはすべてHTTPS(暗号化通信)を利用しているため、ポート番号だけで判断することは困難です。しかし、UTMのアプリケーション制御機能を使えば、こうした通信内容を詳細に識別し、「動画サイトは昼休み中のみ許可」「ファイル共有サービスは特定部署だけ利用可」といったルールを簡単に設定できます。
UTMを導入するメリット
UTMは多機能なセキュリティツールとして知られていますが、実際に導入することで得られるメリットは、単なる防御力の強化にとどまりません。特に中小企業にとっては、人的・金銭的リソースが限られている中で、効率的かつ現実的にセキュリティレベルを引き上げる手段として注目されています。
ここでは、UTMを導入することで得られる4つの主なメリットについて、実務視点で詳しく解説していきます。
セキュリティ対策の一元化
中小企業が抱える大きな課題のひとつに、「セキュリティ対策がバラバラで、全体像を把握できていない」という現実があります。
UTMを導入する最大のメリットは、こうした分散されたセキュリティ対策を1つの機器・管理画面に統合できる点です。各機能が連携して動作するため、設定やポリシーの重複や抜け漏れを防ぎやすくなり、セキュリティ事故のリスクも抑えられます。
また、統一されたログ管理やアラート通知も大きなメリットです。
たとえば、「何が起きたのかをすぐに把握したい」「怪しい動きがあった時に即座に気づきたい」という場合でも、UTMのダッシュボード上で異常が一元的に表示されるため、迅速な判断と対処が可能になります。
このように、UTMによってセキュリティ対策を一元化することで、管理の抜けや属人化を防ぎ、組織全体の安全性を効率的に高めることができます。特に専任の情シス担当者がいない中小企業では、この“まとめて守れる”という特長が大きな安心材料になるはずです。
IT担当者の負担軽減
中小企業では、IT担当者が一人で複数の業務を兼任しているケースが多く、セキュリティ対策に十分な時間やリソースを割けないことが珍しくありません。
社内のパソコン設定、ネットワークトラブル対応、取引先とのWeb会議設定などに追われている中で、ウイルス定義ファイルの更新やアクセスログの確認まで手が回らないという声はよく聞かれます。
UTMを導入することで、そうした担当者の負担を大きく軽減できます。複数のセキュリティ機能が一体化しているため、個別のツールを切り替えて操作する必要がなくなり、ひとつの画面から全体を管理できるようになります。また、アラート通知や自動遮断機能などが標準で搭載されているため、異常が起きても「常時監視」していなくても気づける仕組みが整っています。
導入・運用コストの削減
セキュリティ対策と聞くと、「お金がかかる」というイメージを持たれる方も多いかもしれません。
実際、ファイアウォール、アンチウイルス、VPN、IDSなどをそれぞれ個別に導入した場合、それぞれに初期費用・ライセンス費用・保守費用がかかり、合計するとかなりの出費になります。加えて、それらの管理にも人件費や外注費がかかるため、中小企業にとっては現実的とは言い難い選択肢です。
UTMは、これらの機能をひとつに統合することで、個別導入よりもコストを抑えつつ、一定レベル以上のセキュリティ対策を実現できる点が最大の強みです。
また、UTMの中にはサブスクリプション型で提供されるものもあり、初期費用を最小限に抑えたうえで、必要な期間だけ利用できる柔軟な料金体系が用意されています。これにより、「セキュリティに予算は割きたいが、まとまった資金は出せない」といった企業でも導入のハードルが下がります。
さらに、運用面でもコスト削減が期待できます。異常検知・対応の自動化、設定の簡易化、レポート出力の標準化といった仕組みが整っているため、専門業者に都度依頼する必要が減り、社内での運用が完結しやすくなるのです。
ゼロトラストの第一歩としての活用
ゼロトラストとは、すべての通信を信頼しないことを前提に、常に検証を行いながらアクセスを許可するというセキュリティの考え方です。
これまでのように「社内ネットワークにいるから安全」「一度認証したから大丈夫」といった境界型の発想では、防ぎきれない脅威が増えている現在、ゼロトラストは大企業に限らず、中小企業にとっても必要性が高まりつつあります。
しかし、ゼロトラストの仕組みをいきなり全面導入するのは、多くの中小企業にとってハードルが高いのが現実です。
そこで、第一歩として注目されているのがUTMの導入です。UTMは、通信の検査・ログ取得・アクセス制御といったゼロトラストの基本思想を、既存のネットワーク環境の中に無理なく組み込めるため、「段階的なゼロトラスト化」に最適なツールといえます。
NGFWとUTMはどっちがいい?
UTMを調べていく中で、次世代ファイアウォール(NGFW)という言葉を目にした方も多いかもしれません。UTMとNGFWはいずれもネットワークセキュリティを担う重要な存在ですが、それぞれに特徴や適した用途が異なります。
特に中小企業においては、どちらを選ぶべきかの判断が業務効率やコストパフォーマンスに大きく影響します。ここでは、NGFWの基本的な機能を紹介したうえで、UTMとの違いと選び方について整理していきます。
NGFW(次世代ファイアウォール)とは?
NGFW(Next Generation Firewall)とは、従来のファイアウォール機能に加えて、アプリケーション識別やユーザー単位の制御、SSL復号、脅威インテリジェンス連携などの高度な機能を備えた、いわば進化版のファイアウォールです。通信内容をより詳細に把握し、リスクを自動で評価・対応することができるのが大きな特徴です。
たとえば、NGFWは特定のユーザーが使っているアプリケーション単位で制御をかける、暗号化された通信(HTTPS)を一時的に復号して中身を確認する、といった高度な処理が可能です。これは、攻撃者が従来型のファイアウォールを回避するために巧妙な手口を使ってくる現代において有効なアプローチです。
また、外部の脅威情報と連携し、世界中で観測されている最新のマルウェア情報や攻撃パターンをもとにリアルタイムで対応する仕組みもあります。セキュリティ専門の担当者が常駐するような企業では、こうした高度な制御機能を活用して、きめ細かい運用が行われています。
ただし、これだけの機能をフル活用するには、相応の専門知識と運用体制が必要になります。インターフェースが複雑なことも多く、設定ミスや監視漏れが発生すると、逆にリスクを高めることにもなりかねません。
基本的に中小企業にはUTMがおすすめ
NGFWは確かに高機能であり、大規模な企業や高度なセキュリティ運用が必要な組織には有効な選択肢です。しかし、それらの機能を十分に使いこなすには、ネットワークやセキュリティの専門知識が求められ、社内にセキュリティ担当者が複数名いるような体制でなければ、かえって管理が煩雑になってしまう可能性があります。
その点、UTMは「必要な機能が一通りそろっていて、しかも使いやすい」という点で、中小企業に非常に適しています。専門的な設定やチューニングをしなくても、基本的な防御が自動で行われる設計になっているため、「詳しくなくても、ひとまず安心な状態をつくる」ことができるのです。
また、UTMはサポート体制が手厚い製品も多く、導入時の初期設定から運用後のトラブル対応まで、販売代理店やメーカーの支援を受けやすいのもメリットです。導入後の運用に不安を感じる企業でも、外部パートナーと連携しながら安定したセキュリティ体制を構築できます。
このように、現実的に運用できるセキュリティ対策として、UTMは中小企業にとってベストバランスな選択肢と言えます。限られた人員と予算の中で、最大限のセキュリティ効果を得るためには、まずはUTMから始めることが理にかなったステップです。
UTMに関連するよくある質問
ここでは、UTMに関してよくある基本的な質問を取り上げ、それぞれについて実務目線で分かりやすく回答していきます。
UTMとは何ですか?
UTMとは「統合脅威管理(Unified Threat Management)」の略で、ファイアウォール、ウイルス対策、Webフィルタリング、VPN、IDS/IPSなど、複数のセキュリティ機能を1つにまとめた装置またはクラウドサービスのことを指します。
ファイアウォールとUTMの違いは何ですか?
ファイアウォールは通信の出入り口を制御する機能ですが、UTMはそれに加えてウイルス対策やWebフィルタリングなど複数の機能を統合したセキュリティ対策です。UTMひとつで幅広い脅威に対応できる点が大きな違いです。
中小企業にUTMは必要ですか?
はい、必要です。中小企業はセキュリティ対策が手薄になりがちなため、UTMを導入することで人的リソースをかけずに多面的な防御を実現できます。
UTMを導入している企業の割合は?
明確な統計は業種や企業規模によって異なりますが、ある調査では中小企業の3割程度が何らかのUTM製品を導入しているとされています。特にサイバー攻撃が増加する中で、導入率は年々高まっています。
UTMの設置は義務ですか?
法律でUTMの設置が義務づけられているわけではありませんが、情報漏洩やサイバー攻撃への備えとして導入が強く推奨されています。特に取引先との信頼維持やコンプライアンス対応の観点からも重要です。
UTMの欠点は何ですか?
多機能ゆえに設定が煩雑になったり、製品によってはネットワーク速度に影響を与えることがあります。また、すべての機能を過信せず、定期的な見直しや運用が必要です。
中小企業はUTMの導入を前向きに検討しよう
サイバー攻撃の脅威が年々高度化・巧妙化するなかで、中小企業も「自社は狙われないだろう」という油断はもはや通用しません。むしろ、セキュリティ対策が不十分な企業ほど攻撃の入り口として利用されやすくなっており、取引先や顧客との信頼関係を守るためにも、対策は避けて通れない課題です。
その中で、UTMは限られた人員と予算でも、必要なセキュリティ対策を一元的にカバーできる現実的な選択肢です。専門知識がなくても扱いやすく、外部支援も得られやすいため、自社の規模や業種を問わず、取り入れる価値は十分にあります。
なお、UTMによる社内ネットワークの防御だけでなく、ダークウェブ上での情報漏洩リスクにも目を向けることが重要です。社員のメールアドレスやパスワード、顧客データなどがダークウェブで売買されるケースも増えており、被害に気づかないまま取引先や顧客に迷惑をかけてしまう恐れもあります。
外部の不正利用をいち早く察知するためには、ダークウェブ監視サービスの活用が有効です。UTMとあわせて導入することで、内部からの侵入と外部への情報拡散の両面に備えることができ、より堅牢なセキュリティ体制を構築できます。
弊社では、漏洩の有無を確認できるダークウェブ監視サービスの無料デモをご提供しています。中小企業こそ、攻撃を受ける前に見えない脅威を知ることが最善の防御です。ぜひこの機会にご体験ください。