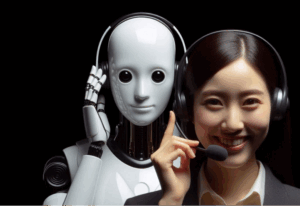クラウドサービスの普及が急速に進む中で、セキュリティ上の懸念が増大しています。
従来のオンプレミス環境と異なり、クラウド利用ではデータがインターネットを介してやり取りされるため、情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まります。この課題を解決するのが「CASB(Cloud Access Security Broker)」です。
本記事では、CASBの基本的な仕組みや重要性、その機能やメリット、さらには導入方法について詳しく解説します。
CASBとは
CASB(Cloud Access Security Broker)は、企業ネットワークとクラウドサービスの間に位置し、データを安全に扱うための管理や監視を行います。
最近ではクラウドサービスの利用が一般化し、企業の大切なデータがクラウド上に保存される機会が増えていますが、その一方でセキュリティリスクも高まっています。こうした課題を解決するために、CASBは重要な役割を果たします。
具体的に、CASBはクラウド利用に伴う以下のような課題を解決します。
- クラウドサービスの利用状況を把握できていない(いわゆる「シャドーIT」)。
- どのデータがどのように利用されているのか見えない。
- サイバー攻撃や不正アクセスのリスクが高い。
これらの課題に対して、CASBは「データの保護」「アクセス管理」「リスクの可視化」といった強力な機能を提供し、企業が安心してクラウドを活用できる環境を整えるのです。
CASBの仕組み
CASBは、企業が利用するクラウドサービス(例えば、Google WorkspaceやMicrosoft 365など)と直接連携し、データやアクセスの動きを監視・制御します。この仕組みにより、どの従業員が、どのデバイスから、どのデータを操作しているのかを詳細に把握できます。
たとえば、ある従業員が社外の未許可のクラウドストレージに会社の機密情報をアップロードしようとした場合、CASBはこれを検知してアップロードをブロックすることが可能です。また、悪意のある外部ユーザーが従業員のアカウントを乗っ取った場合も、その異常な動きを察知して、迅速に対応することができます。
CASBが重要な理由
CASBが注目される背景には、近年の働き方やIT環境の変化があります。クラウドサービスの利用増加やリモートワークの普及に伴い、従来のセキュリティ対策では対応しきれない新たな課題が生まれているのです。
ここでは、CASBが重要視される理由を、具体的な事例とともに分かりやすく解説します。
クラウド利用の増加
企業が日々の業務を効率化するためにクラウドサービスを利用するケースが急増しています。例えば、Google WorkspaceやMicrosoft 365といったコラボレーションツール、DropboxやBoxといったクラウドストレージサービスなど、クラウドベースのツールが業務の中心となっている企業も少なくありません。
このような状況において、次のような課題が浮き彫りになっています。
- どのクラウドサービスが利用されているか把握できない。
- 社員が個人的に導入したサービス(シャドーIT)が潜在的リスクを引き起こす可能性がある。
- クラウド上のデータが企業のセキュリティポリシーに準拠していないケースがある。
CASBは、これらの課題を解決するため、クラウド利用を「見える化」し、安全に管理するためのツールとして必要不可欠です。
リモートワークの普及
新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに、リモートワークが急速に広まりました。
オフィスに限らず、自宅やカフェなど、あらゆる場所からクラウドサービスにアクセスすることが当たり前になりつつあります。この柔軟な働き方には多くのメリットがありますが、一方でセキュリティ面での新たなリスクも生まれています。
- 社外ネットワーク(Wi-Fi)の利用に伴う通信の傍受リスク。
- 従業員個人のデバイスを利用することで起きるセキュリティポリシーの不統一。
- アクセス管理が不十分なために、アカウントの乗っ取りや不正アクセスが発生。
CASBは、リモートワーク環境においても、アクセス権の管理や通信の暗号化、デバイスの監視といった機能を提供します。これにより、社員がどこからアクセスしても安全に業務を行える環境を実現します。
セキュリティとコンプライアンス
クラウド利用が進む中で、企業はセキュリティリスクへの対応だけでなく、各種の法規制や業界標準を守る必要があります。特に、個人情報や機密情報を扱う業界では、GDPR(EU一般データ保護規則)やHIPAA(米国医療保険の携行性と責任に関する法律)などの規制を遵守しなければいけません。
CASBは、クラウド上のデータがどのように扱われているかを監視し、企業が定めたポリシーに違反する操作を未然に防ぎます。また、規制遵守の証拠となるログや監査証跡を提供する機能も備えており、法令対応をサポートします。
なぜ従来のセキュリティ対策では不十分なのか?
これまでのセキュリティ対策は、主に企業のネットワーク内部を守ることに重点を置いていました。ファイアウォールやウイルス対策ソフト、VPNといった技術は、社内ネットワークを利用している前提で設計されているため、クラウドサービスを前提とした働き方やリモートワーク環境では、その効果が限定的です。
例えば、社員が自宅から個人のスマートフォンを使ってクラウドサービスにアクセスする場合、社内ネットワークを経由しないため、従来のファイアウォールではその行動を監視することができません。このような状況下でCASBは、ネットワークの内外を問わず、クラウド利用を統合的に管理・保護するためのソリューションとして機能します。
CASBの主な機能
ここでは、CASBの主な機能について具体例を交えながら分かりやすく解説します。
データ保護
CASBの最も重要な機能の一つが、クラウド上で扱われるデータの保護です。
クラウド環境では、企業がデータを直接管理するのが難しくなる理由として、サードパーティのサービスに依存することや、アクセス権限の分散化が挙げられます。このような状況では、データ漏洩や不正な共有といったリスクが高まるため、適切な管理とセキュリティ対策が不可欠です。
CASBはこれらの課題に対処するため、データの暗号化、不正アクセスの検知、そしてアクセス制御ポリシーの適用など、多面的な保護機能を提供します。たとえば、クラウドストレージに保存された機密情報に対して自動的に暗号化を施し、未承認のユーザーによるアクセスを遮断する仕組みを導入できます。
このようにして、クラウド環境でも企業が安心してデータを運用できる基盤を構築します。
脅威検出
クラウド環境におけるサイバー攻撃や内部不正をいち早く検知することも、CASBの重要な役割の一つです。
クラウド環境では、DDoS攻撃やフィッシング攻撃といった外部からの脅威だけでなく、内部ユーザーによる意図的または偶発的なデータ漏洩など、多様なリスクが存在します。これらのリスクを見逃さないために、CASBはAIや機械学習を活用した高度な分析技術を駆使しています。
この仕組みにより、CASBは単なる監視ツールではなく、クラウド環境のセキュリティを強化するための防御策として機能します。
可視化
クラウドサービスが社内外でどのように利用されているのかを「見える化」する機能も、CASBが提供する重要な特長です。この機能では、たとえば以下のようなデータがリアルタイムで可視化されます。
- ユーザーごとのクラウド利用状況: 誰が、いつ、どのサービスにアクセスしたか。
- データ転送の詳細: どのファイルがどこにアップロードまたはダウンロードされたか。
- 外部共有の状況: 機密情報が不適切に外部共有されていないか。
この「見える化」により、情報システム部門はこれまで把握しきれなかったシャドーITの存在や、予期しないデータの流れを迅速に発見できます。
CASBを導入するメリット
前のセクションで紹介した機能がどのようなメリットを生むのかを見ていきましょう。
セキュリティ強化
クラウドサービスを利用する際、多くの企業が直面する最大の懸念はセキュリティリスクです。これには、データ漏洩、認証情報の不正利用、そしてサイバー攻撃による業務停止などが含まれます。
これらのリスクは、クラウドの柔軟性を享受する一方で、従来型のセキュリティ対策では対応が難しいという課題を伴います。
CASBを導入することで、これらのセキュリティリスクを大幅に軽減し、より安全にクラウドサービスを利用できるようになります。たとえば、CASBは以下のようなセキュリティ強化策を提供します。
- リアルタイム監視とアラート: 異常なアクセスや不審なデータ操作を即座に検知し、管理者に通知。
- データ保護ポリシーの適用: 機密情報の暗号化や、特定の条件下での外部共有のブロック。
- アクセス制御の強化: ユーザーやデバイスごとに細かく設定可能なアクセス許可。
このように、CASBは単なるセキュリティツールではなく、クラウド時代における包括的な防御基盤として機能します。
コンプライアンス対応
情報漏洩のリスクが高まる中、多くの企業が直面する課題の一つに、GDPRやCCPAといった厳格な法規制への対応があります。これらの規制では、個人データの収集、処理、保存、そして共有に関する厳しい基準が求められ、違反すれば多額の罰金や信頼喪失といった重大なリスクを伴います。
CASBは、企業がこれらのコンプライアンス要件を満たす上で、以下のような機能を提供します。
- データ分類とポリシー適用: クラウド上のデータを自動的にスキャンし、個人データや機密情報を識別。それに基づき適切な保護ポリシーを適用します。
- アクセスログの管理: データのアクセスや利用履歴を記録・保存し、規制当局への監査対応を容易にします。
- データ転送の制御: 個人データが許可されていない地域(例:EU外)に転送されるのを防ぐ地理的制御を実現します。
これにより、企業はコンプライアンス対応にかかる負担を軽減しつつ、法規制の要件を確実に満たすことができます。
業務効率の向上
CASBはセキュリティを強化するだけでなく、業務効率を向上させるツールとしても機能します。クラウド環境では、膨大なデータやアクティビティを管理する必要があり、従来の手作業や分散した管理システムでは効率が悪くなるケースが多々あります。CASBはこれを解決し、業務をスムーズに進めるための仕組みを構築するのです。
たとえば、以下のような機能が業務効率化に寄与します。
- ポリシーの一元管理: 各クラウドサービスに個別設定していたセキュリティポリシーを、CASB上で一括管理。設定ミスや重複作業を減らし、IT部門の負担を軽減します。
- 自動化された監視と対応: リアルタイムの異常検知や、ポリシー違反が発生した際の自動アクション(例:アクセスブロックや通知)により、手動での対応時間を削減します。
- 可視化による意思決定の迅速化: データ利用状況やリスクの把握が容易になるため、迅速かつ的確な意思決定が可能になります。
このように、CASBはセキュリティ管理を効率化するだけでなく、業務全体の生産性向上を支える重要なツールです。
CASBを導入するデメリット
CASBは、クラウド利用に伴うセキュリティリスクを大幅に軽減する一方で、導入や運用にはいくつかの課題やデメリットも存在します。ここでは、CASB導入にあたり注意すべきポイントを詳しく解説します。
導入コスト
CASBを導入する際、多くの企業が直面する課題の一つが「コスト」の問題です。初期導入費用やライセンス料、運用コストが発生するため、特に中小企業やIT予算に限りがある企業にとっては慎重な検討が求められます。
しかし、これらのコストは必ずしも導入の障壁にはなりません。以下のようなポイントを考慮することで、費用対効果を最大化できます。
- サブスクリプションモデルの活用: 多くのCASB製品は月額または年額で利用できるサブスクリプション型の料金体系を採用しており、初期投資を抑えつつ必要な機能を柔軟に選択できます。
- リスク削減によるコスト削減効果: データ漏洩やサイバー攻撃が発生した場合の損害を考慮すると、CASBの導入によるリスク回避は結果的にコストを節約する手段ともいえます。
- スケーラブルな導入: 企業規模や予算に応じて、必要最低限の機能から段階的に拡張できるプランを選ぶことが可能です。
CASBの導入は単なる費用ではなく、セキュリティと業務効率を同時に高め、長期的にはコスト削減にも寄与する戦略的な投資と言えます。
従業員の意識改革
CASBはセキュリティ対策ツールとして強力ですが、従業員がその存在や目的を正しく理解していない場合、その効果を最大限に発揮することは難しくなります。セキュリティの強化は、技術的な対策だけでは不十分であり、従業員一人ひとりの協力が不可欠です。
具体的には、以下のような課題が考えられます。
- セキュリティポリシーの無理解: 従業員がCASBを通じて適用されるセキュリティポリシーを知らないと、不適切なデータ共有やクラウドサービスの利用が続く可能性があります。
- シャドーITの利用: 情報システム部門の管理外でクラウドサービスを利用する行動が、CASBの監視範囲を逸脱する原因となります。
- 対策への抵抗感: セキュリティ強化が業務効率の妨げになると誤解され、従業員の協力を得られない場合もあります。
こうした課題に対応するためにも、定期的なセキュリティ教育を実施し、従業員の意識改革を進めなければいけません。
CASBの活用シーン
本セクションでは、CASBが実際にどのようなシーンで役立つのか、具体例を交えながら分かりやすく説明します。
シャドーITの防止
シャドーITとは、企業が許可していないクラウドサービスやアプリケーションが従業員によって使用される状況を指します。この問題は、多くの企業でセキュリティリスクの一因となっています。
例えば、営業チームが社内のクラウドストレージが使いにくいと感じ、勝手に無料のクラウドサービスを利用して顧客情報を共有するケースがあります。この場合、企業はそのサービスが安全かどうかを把握できず、情報漏洩や法令違反のリスクが高まるのです。
CASBは、ネットワークやクラウドサービスのトラフィックを監視し、従業員が利用しているクラウドサービスを検出します。その後、許可されていないサービスについて警告を出したり、利用を制限したりすることが可能です。
データ流出の防止
クラウドサービスを利用する際に特に懸念されるのが、機密データの流出です。社内外を問わず、情報が不適切に共有されるリスクは常に存在します。
例えば、従業員が業務に必要なデータを個人のクラウドストレージにアップロードし、そのまま退職してしまった場合、企業はそのデータを取り戻せない可能性があります。また、外部の取引先に資料を送る際、誤って関係のない相手に送信してしまうケースも考えられます。
CASBは、クラウド上で扱われるデータにポリシーを設定し、特定のデータが外部に転送されるのを自動的にブロックできます。また、送信前にアラートを表示し、操作の再確認を促すことで、人為的なミスを未然に防ぐことも可能です。
リモートワークのセキュリティ強化
リモートワークの普及により、従業員がさまざまな場所からクラウドサービスにアクセスするケースが増えています。この柔軟な働き方には利便性がある一方で、セキュリティリスクも高まるのです。
社員が自宅やカフェなどの安全性が保証されないWi-Fiを使ってクラウドにアクセスする場合、通信が傍受される可能性があります。また、業務で使用するデバイスが適切に保護されていない場合、マルウェア感染や不正アクセスのリスクも存在します。
CASBは、どのデバイスから、どのネットワークを経由してクラウドにアクセスしているのかをリアルタイムで監視します。不審なアクセスを検知すると即座にブロックし、セキュリティを確保。また、多要素認証(MFA)を導入することで、リモート環境における認証を強化します。
CASBの導入方式
CASBは、その機能の多様性に加えて、導入方式も企業の要件や環境に応じて柔軟に選べるのが特徴です。ここでは、主な導入方式である「APIベース」「プロキシベース」「ハイブリッド型」のそれぞれの仕組みと特徴を詳しく解説します。
APIベースの導入方式
APIベースのCASBは、クラウドサービスが提供するAPIを活用して、クラウド内のデータや操作を直接管理・監視する方式です。
APIを利用することで、クラウドサービスの内部にあるデータや設定に直接アクセスします。この方法は、クラウドサービス自体がAPI連携をサポートしている場合に有効であり、Google WorkspaceやMicrosoft 365のような主要なクラウドサービスでは一般的です。
APIベースのメリットとしては、以下のようなものがあげられます。
- 設定が簡単:プロキシの設置が不要で、既存のネットワーク構成を変更する必要がありません。
- データへの深いアクセス:クラウド上のデータ、共有設定、ログイン履歴など、詳細な情報を取得可能です。
- リアルタイム性:APIを通じてほぼリアルタイムに監視と制御が行えます。
一方で、利用するクラウドサービスがAPIに対応していなければ導入できない、データの流れの監視が苦手というデメリットもあります。
プロキシベースの導入方式
プロキシベースのCASBは、クラウドサービスとの通信をプロキシサーバ経由にすることで、データの流れを監視・制御する方式です。
従業員がクラウドサービスにアクセスする際のトラフィックをプロキシサーバに中継させることで、すべてのデータ通信をリアルタイムで監視します。
プロキシベースのCASBには以下のメリットがあります。
- 通信内容の完全な可視化:クラウドへのアクセスやデータ転送など、ネットワーク上のトラフィックを詳細に監視できます。
- リアルタイムでの制御:プロキシを経由するため、不適切な通信を即座にブロックすることが可能です。
- シャドーITの検出:許可されていないクラウドサービスの利用も検出できます。
大きなデメリットとしては、プロキシを導入するため、既存のネットワーク構成に手を加える必要がある点が挙げられます。また、通信速度の遅延やリモートワークに完全対応できないのもデメリットでしょう。
ハイブリッド型の導入方式
ハイブリッド型のCASBは、APIベースとプロキシベースの両方の機能を組み合わせた方式です。クラウドサービスの特性や利用環境に応じて、最適な監視方法を選択できる柔軟な導入ができます。
簡単に特徴を説明すると、APIを利用してクラウドサービス内のデータを監視しつつ、プロキシでネットワークトラフィックを管理することで、二重のセキュリティを提供するというものです。
主なメリットは以下の通りです。
- 包括的なセキュリティ:クラウド内のデータもトラフィックも同時に監視・制御できるため、全体的なセキュリティレベルが向上します。
- 柔軟性の向上:異なるクラウドサービスや利用シナリオに応じて、最適なアプローチを採用可能です。
- リモートワークにも対応:リモートアクセス時のプロキシを補完する形でAPIを利用できるため、柔軟な対応が可能です。
一方で、次のようなデメリットも生じます。
- コストが高くなる可能性:両方式を組み合わせるため、導入・運用費用が高くなる場合があります。
- 管理の複雑化:2つの仕組みを組み合わせるため、運用や設定に手間がかかることがあります。
導入方式の選び方
3つの導入方式を見てきましたが、自社に最適な方式がわからないという方もいるでしょう。そこで各方式が向いているケースをご紹介します。
【APIベースが適している場合】
- 使用しているクラウドサービスがAPI連携をサポートしている。
- ネットワークの構成変更を最小限に抑えたい。
- クラウド上のデータや操作を重点的に管理したい。
【プロキシベースが適している場合】
- シャドーITや通信内容をリアルタイムで監視したい。
- 社内ネットワークでのセキュリティを強化したい。
- 許可されていないクラウドサービスの利用を即座に制御したい。
【ハイブリッド型が適している場合】
- 幅広いクラウドサービスを利用している。
- リモートワークや社外アクセスのセキュリティを強化したい。
- 包括的かつ柔軟なセキュリティソリューションを求めている。
まとめ
CASBを導入することで、複数のクラウドサービスを一元的に管理できるようになり、自社のセキュリティを大幅に向上させることが可能です。これにより、データ漏洩や不正アクセスなどのリスクを抑えながら、クラウド環境を安全に利用できます。
しかし、日々高度化するサイバー攻撃の前では、100%完璧な対策は存在しません。
たとえば、従業員が簡単なパスワードを使用したり、セキュリティポリシーを無視した場合には、CASBの強力な防御網をすり抜けて攻撃の糸口になる可能性があります。そのため、CASBの運用と併せて、サイバー攻撃の被害を最小限に抑えるための対策を講じることが重要です。
こうしたリスク管理を強化する手段の一つが「ダークウェブ監視」です。
ダークウェブ上には、企業の認証情報や顧客データが取引されているケースがあり、これがサイバー攻撃の準備段階で利用されることも少なくありません。CASBによるセキュリティ対策に加え、ダークウェブを監視して漏洩の兆候を早期に発見することで、より堅牢なセキュリティ体制を構築できます。
弊社が提供するダークウェブ監視サービス「ZeroDarkWeb」は、ダークウェブ上の情報を継続的に監視し、従業員や顧客の認証情報が不正に流出していないかを検知。問題が発見された場合には迅速に通知し、対策を講じるサポートを行います。
ぜひ、「ZeroDarkWeb」の無料デモにお申し込みいただき、自社のセキュリティをさらに強化していただければと思います。
弊社はダークウェブ調査(無料)を実施しています。
こちらからお申し込みください。