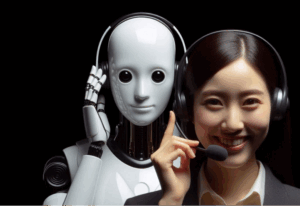現代の企業活動において、ITツールの活用はもはや前提条件です。しかし、その裏で管理者の目が届かない「シャドーIT」が急増している現状をご存じでしょうか。
社員が正式に承認されていないツールを勝手に使用し、便利さを求めた結果、セキュリティリスクを招いてしまう──これは多くの企業が直面する課題です。
この課題を解決するために注目されているのが「サンクションIT」です。企業が承認したツールだけを利用することで、リスクを最小限に抑えながら、IT資産の透明性と業務効率を高められます。
特に、シャドーITや個人端末の業務利用(BYOD)といったトピックとの関連性は深く、対策の第一歩として取り入れる企業が増えています。
本記事では、サンクションITの基本的な仕組みから、シャドーITやBYODとの違い、セキュリティリスクへの具体的な対策までを徹底解説します。
サンクションITとは
「サンクション(sanction)」は「許可」や「承認」を意味し、サンクションITとは、企業が正式に承認したITツールやシステムのことです。
たとえば、営業部門が顧客情報を管理するために使用するCRM(顧客管理システム)や、プロジェクト進行を管理する「Trello」「Asana」といったタスク管理ツール。また、コミュニケーションツールである「Microsoft Teams」や「Slack」も、企業が承認すればサンクションITに分類されます。
サンクションITが注目される理由は、主に次の二つです。
- セキュリティリスクの軽減
サンクションITは、外部からの攻撃や情報漏洩に対するセキュリティ対策が十分に施されているため、安心して利用できるツールです。たとえば、許可されていないツールを使用する「シャドーIT」が引き起こすリスクと比較すると、安全性は圧倒的に高まります。
- 利用状況の可視化と管理
承認されたツールには、企業が使用状況を監視する仕組みが整っています。不正利用や誤操作が発生しても即座に対応でき、トラブルを最小限に抑えられます。
近年多発するフィッシング詐欺や情報漏洩事件への対策としても、サンクションITの導入は効果的です。特に、社員が複数のツールを使い分けることで管理が複雑化するリスクを軽減し、IT資産の透明性を確保する点で多くの企業が採用を進めています。
こうした理由から、サンクションITは単なるツール群ではなく、企業の信頼性と生産性を支える重要なインフラとして位置付けられています
シャドーITとの違い
サンクションITの反対の概念としてよく挙げられるのが「シャドーIT」です。
シャドーITとは、企業が承認していないにもかかわらず、従業員が業務で使用しているITツールやサービスのことを指します。「影のIT」という意味で、企業のIT管理者がその存在を知らない、または管理できていない状態を表しています。
例を挙げると、企業が提供する公式のクラウドストレージサービスがあるにもかかわらず、従業員が個人的にGoogleドライブやDropboxを使用して業務データを共有しているケースはシャドーITに該当します。
シャドーITの最大の問題点は、企業がセキュリティ管理を行えないという点です。こうした管理外のツールでは、以下のようなリスクが生じます。
- 機密データが外部のサーバーに保存され、不正アクセスや情報漏洩の危険が高まる。
- アクセス権限が適切に管理されておらず、元従業員や第三者が容易に情報にアクセスできる可能性がある。
- ツール自体に脆弱性があり、サイバー攻撃の対象になるリスクがある。
これらのリスクを避けるためには、IT管理部門がシャドーITの存在を把握し、必要であればその利用を制限したり、代わりに安全で効率的なサンクションITを導入したりすることが重要です。
BYODとの違い
もう一つ、サンクションITと混同されやすい概念が「BYOD」です。
BYODとは「Bring Your Own Device」の略で、従業員が個人所有のデバイス(スマートフォンやノートパソコンなど)を業務に使用することを指します。サンクションITが「使用するツールやシステムの承認」を意味するのに対し、BYODは「使用するデバイスが企業所有か個人所有か」に注目している点が異なります。
たとえば、BYODを許可している場合、従業員は自分のスマートフォンを使ってメールやチャットツールを利用できます。
ただし、これがサンクションITに該当するかどうかは、企業がそのデバイスやツールを公式に許可しているかどうかによります。もし企業が特定のチャットアプリを公式に許可しているのであれば、それはBYOD環境におけるサンクションITの一例と言えます。
BYODにはコスト削減や柔軟性向上といった利点がありますが、セキュリティリスクが伴います。具体的には、個人デバイスには企業が管理できないアプリや設定が含まれている場合があり、不正アクセスやデータ流出のリスクが高まります。
そのため、BYODを実施する際にも、サンクションITとして企業が許可したツールを利用し、それを厳密に管理しなければいけません。
サンクションITの導入が必要な理由
現代の企業活動では、サンクションITの導入が必須といえる状況になりつつあります。以下では、その理由を紐解いていきましょう。
シャドーITのリスク
シャドーITの利用が企業内で増加する主な理由として、従業員が「企業がしているツールが使いづらい」「もっと効率的なツールを使いたい」と感じることが挙げられます。
一見すると、従業員が業務を効率化するためにツールを活用しているだけであり、問題はないように思えるかもしれませんが、シャドーITの利用は深刻なリスクを伴います。
その一例として、セキュリティ侵害を挙げられます。シャドーITを通じて業務データや機密情報が漏洩するケースは後を絶ちません。個人で契約したクラウドストレージに業務データを保存した場合、そのプラットフォームが適切なセキュリティ対策を実施していないと、第三者による不正アクセスのリスクが発生します。
また、シャドーITの利用によって企業のシステムが複雑化し、IT部門が全体を把握できなくなり、適切なメンテナンスや脆弱性への対応が困難になるリスクも招くのです。
このようなリスクを軽減するためには、サンクションITの導入が重要です。企業が公式に承認したツールを提供し、それを利用するよう従業員を促すことで、シャドーITの利用を抑えつつセキュリティを強化できます。
セキュリティガバナンスの重要性
セキュリティガバナンスとは、自社の情報資産を守るために設けるルールやプロセスのことです。これが適切に機能しない場合、サイバー攻撃や内部不正が発生しやすくなります。
特に近年、ランサムウェアやフィッシング攻撃といった高度なサイバー攻撃が増加しており、セキュリティリスクへの対応の重要性が増しています。
サンクションITにすることで、各種ツールの使用状況をモニタリングし、不審な活動や脅威を早期に検知することが可能です。また、従業員が安全な環境で業務を遂行できるよう支援することで、全体的なセキュリティ意識の向上にもつながるでしょう。
規制対応とコンプライアンス
近年、多くの国や地域で情報保護に関する法律や規制が整備されてきました。欧州連合(EU)のGDPR(一般データ保護規則)や、アメリカのCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)などは、その代表例です。
これらの規制では、個人データの管理や保護に関する厳格な要件が定められており、違反すると多額の罰金や訴訟リスクに直面する可能性があります。
規制対応の観点からも、サンクションITの導入は重要です。
企業が公式に承認したITツールを使用することで、データの管理が一元化され、必要に応じて監査証跡を容易に提供できます。さらに、規制に対応するためのコストや手間の削減も可能です。
シャドーITを後から取り締まったり、リスクのあるデータを追跡したりするよりも、あらかじめ承認済みのツールを使用して一元的に管理する方が効率的なためです。
サンクションITが抱えるセキュリティリスク
サンクションITは、企業のITガバナンスを支える重要なツールですが、導入しただけで完全にリスクが排除されるわけではありません。
むしろ、企業が承認したツールであるからこそ、その運用が適切でなければ新たなセキュリティリスクが発生する可能性があります。以下では、サンクションITが抱える代表的なセキュリティリスクについて解説します。
1. 不正アクセスによるシステム侵害
サンクションITにおいても見過ごせないリスクの一つが、不正アクセスによるシステムの侵害です。
たとえば、従業員が利用するサンクションITのログイン情報(IDやパスワード)が流出した場合、攻撃者は正規ユーザーを装って企業のシステムに侵入できます。このような侵害が発生すると、以下のような被害が起こります。
- 重要データの盗難
機密情報や顧客データが外部に漏洩すれば、信用失墜や法的な罰則を受けるリスクがあります。
- ランサムウェア攻撃による業務停止
攻撃者がシステム内のデータを暗号化し、復旧のための身代金を要求するケースも増加しています。こうした攻撃は、業務の中断だけでなく、復旧費用や対応に要するリソースといった多大なコストを招きます。
さらに近年では、従業員のログイン情報を盗むためにフィッシング詐欺やリスト型攻撃(流出した情報を基にしたアカウント不正利用)といった手口が巧妙化しており、企業側の対策が追いつかない場合もあります。
2. 従業員の操作ミスや意識不足
どれほど優れたセキュリティ対策を導入しても、従業員の操作ミスやセキュリティ意識の不足が原因でリスクが発生するケースは避けられません。サンクションITの利用においても、人為的なエラーが企業の重要データを危険にさらすことがあります。
たとえば以下のようなケースです。
- 誤ったデータ共有
重要データを誤ってアップロードし、そのデータが外部からアクセス可能な状態で公開されてしまうケース。クラウドストレージの公開設定ミスが原因で、機密情報が外部に流出する事例は珍しくありません。
- 不適切な外部連携
従業員が承認されていない外部ツールとサンクションITを連携し、データが想定外の範囲に拡散するリスクがあります。また、共有リンクを不特定多数に送信した結果、予期せぬ相手にデータが渡る事態も起こり得ます。
- フィッシング詐欺への対応ミス
セキュリティ意識の低い従業員が、不審なメールを信じてパスワードを入力し、攻撃者に情報を渡してしまうケース。こうしたミスは、個人だけでなく、企業全体に被害を及ぼす可能性があります。
サンクションITを最大限に活用するためには、ツールの性能に頼るだけでなく、人と技術が一体となってリスクを未然に防ぐ仕組みを構築することが不可欠です。
3. ツールやシステムの脆弱性
サンクションITのツール自体に脆弱性が存在する場合もリスクとなります。
多くのITツールはアップデートやパッチの適用によって安全性を保っていますが、これを怠ると脆弱性が残り、それを狙った攻撃の対象になります。
そのため、定期的に各種ツールに脆弱性がないかの確認をし、脆弱性が複数ある場合は迅速に優先順位をつけて適切に対応しなければいけません。すべてのITツールを把握できるサンクションITの環境を構築しても、対応の遅れや漏れがあればリスクが拡大します。
4. 内部不正のリスク
サンクションITの利用は管理が行き届いている一方で、アクセス権限の適切な設定がされていなければ内部不正の温床になる可能性が高いです。
すべての従業員に同じレベルのアクセス権限を付与するとしましょう。この場合、必要以上の情報にアクセスできる従業員が発生し、不正行為や情報漏洩のリスクが高まります。
特に、退職予定の従業員が機密情報を外部に持ち出すといったケースは多く報告されています。こうしたリスクを防ぐためには、適切なアクセス権限の管理をしなければいけません。
サンクションITのセキュリティを高めるポイント
サンクションITの効果を最大化し、セキュリティリスクを最小限に抑えるためには、適切な運用が不可欠です。ここからは、サンクションITのセキュリティを高めるための具体的な対策について解説します。
1. 強力なパスワード設定と多要素認証の導入
最も基本的でありながら、非常に重要な対策が「強力なパスワード」の設定と「多要素認証(MFA: Multi-Factor Authentication)」の導入です。
従業員のパスワードが容易な場合、悪意ある第三者が簡単に不正アクセスを行えます。それでは、どのようなパスワードを設定するべきでしょうか。強力なパスワードとは、以下のような条件を満たすものです。
- 英大文字、小文字、数字、記号を組み合わせた12文字以上の長さ
- 辞書に載っている単語や簡単な組み合わせ(「password123」など)を避ける
- 複数のサービスで同じパスワードを使用しない
これに加えて、多要素認証を導入することで、セキュリティをさらに向上させられます。
多要素認証は、IDとパスワードだけではなく、追加の認証要素(スマートフォンに送られる認証コードや指紋認証など)を求める仕組みです。これにより、仮にパスワードが流出しても、攻撃者がシステムにアクセスすることを防げます。
2. アクセス権限の最適化
サンクションITのセキュリティを高めるためには、従業員ごとに適切なアクセス権限を付与することが重要です。アクセス権限を設定する際、以下のような原則に従うようにしましょう。
- 最小権限の原則(Least Privilege Principle):従業員には、その業務に必要最低限の権限のみを付与する。例えば、一般従業員が全社の財務データにアクセスできる必要はありません。
- 役割ベースのアクセス制御(RBAC: Role-Based Access Control):従業員の役割に基づいて、事前に定義された権限を割り当てる。
また、アクセス権限は一度設定すれば終わりではなく、定期的に見直さなければいけません。退職した従業員や異動した従業員の権限をそのまま放置することは、内部不正のリスクを高めるため、速やかに対応する必要があります。
3. 従業員教育の実施
サンクションITのセキュリティを高めるには、ツールやシステムの設定だけでは不十分です。最終的には、それを使う従業員の意識が重要な鍵となります。セキュリティ教育を通じて、従業員に以下のような知識と習慣を身につけてもらいましょう。
- フィッシングメールへの対処法:不審なメールの特徴や、リンクをクリックする前に確認すべきポイントを教える。
- シャドーITの危険性:公式に承認されていないツールを使用するリスクを理解してもらう。
- パスワード管理の重要性:パスワードマネージャーの利用を推奨し、安全なパスワードの作成と管理を促進する。
初回の研修だけでなく、定期的に実施し、従業員が最新の脅威や対策について理解を深めることが重要です。
4. 定期的なセキュリティ評価の実施
IT環境は日々進化しており、過去には問題がなかったシステムでも新たな脆弱性が発見されることがあります。このようなリスクを見逃さないためには、継続的な評価が必要です。
評価の主な目的は、新しい脅威への対応だけでなく、既存のセキュリティポリシーがツールや運用に適合しているかを確認し、不足があれば補強することにあります。
また、従業員がセキュリティルールを遵守しているかを点検し、不適切な運用が見つかった場合には改善を図らなければいけません。
セキュリティ評価は自動スキャンや第三者機関の診断を活用しつつ、日常的な運用の中でリアルタイム監視を組み合わせると効果的です。これを継続することで、新たな脅威を迅速に発見し、企業全体のセキュリティレベルを高い状態で維持することが可能になります。
サンクションITに関するよくあるQ&A
最後に、サンクションITに関するよくある質問とその答えを分かりやすく解説します。
Q1: サンクションITとシャドーITの違いは何ですか?
サンクションITは企業が正式に承認したツールであり、管理下に置かれているのに対し、シャドーITは企業の管理外にあるツールやサービスを指します。
Q2:サンクションITとBYODの違いは何ですか?
BYODはデバイスの所有形態に着目した概念であり、サンクションITは使用されるツールやサービスが承認されているかに焦点を当てています。BYOD環境でもサンクションITを適切に利用することで、安全性を確保できます。
Q3:サンクションITのセキュリティリスクはどのように対策できますか?
強固なパスワード設定、多要素認証の導入、アクセス権限の適正化、従業員教育、そして定期的なセキュリティ評価を行うことがリスク軽減につながります。
まとめ
サンクションITは、シャドーITがもたらすリスクを回避し、企業のIT環境を安全に保つための重要な手段です。しかし、その導入においても万全のセキュリティ対策が求められます。本記事で紹介したポイントを押さえ、サンクションITの効果を最大限に引き出すことで、企業のITガバナンスと成長を両立させることが可能です。
加えて、近年はダークウェブでの情報漏洩リスクが大きな課題となっています。ダークウェブは匿名性の高いインターネット空間で、盗まれたログイン情報や機密データが取引される場です。これらを見逃せば、企業の信頼や財務に甚大な被害をもたらす可能性があります。
弊社が提供するダークウェブ監視サービス「ZeroDarkWeb」では、こうしたリスクを早期に発見し、迅速な対応を支援します。ただいま無料デモを実施中ですので、この機会にぜひお試しください。お申し込みは以下のリンクからどうぞ。
弊社はダークウェブ調査(無料)を実施しています。
こちらからお申し込みください。