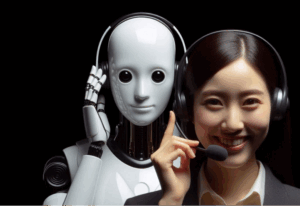そのUSBメモリ、何気なく挿していませんか?
近年、サイバー攻撃の手口はますます巧妙化し、私たちが軽視しがちなアナログな入口を狙うケースが増えています。とりわけUSBメモリを介した攻撃は、静かに、しかし確実に情報資産を侵害しています。
たとえば、会議資料を保存しただけのUSBメモリが発端となり、社内ネットワーク全体がマルウェアに感染した例、拾ったUSBメモリを何気なく挿したことで顧客情報が流出した事件などは、もはや他人事ではありません。クラウド活用が進む一方で、物理デバイスに対する警戒は薄れつつあります。
USBメモリはその利便性ゆえに、今なお多くのビジネス現場で使用されていますが、その背後には見過ごされがちなセキュリティリスクが潜んでいます。
本記事では、USBメモリを標的とした攻撃の実態、攻撃者の手法、そしてすぐに取り組める対策までを専門的に解説します。
「USBメモリは便利で安全」という思い込みが、情報漏洩や業務停止の引き金となる前に。まずは、そのリスクを正しく理解することから始めましょう。
なぜUSBメモリにセキュリティ対策が必要なのか?
USBメモリは「手軽に持ち運べるデータ保存手段」として広く利用されています。しかし、この利便性が裏目に出る場面も少なくありません。物理的に小さく、誰でも簡単に使用でき、どこでも接続可能であることから、セキュリティホールとして狙われやすいのです。
また、USBメモリは企業が管理しにくい資産の代表例でもあります。
IT資産として登録されず、棚卸しや追跡が行われないまま紛失するケース、退職者が私物として持ち出すケースも少なくありません。こうした背景から、内部からの情報漏洩リスクも高まっています。
USBメモリは目に見える媒体であるため安心感を抱かれがちですが、それが最大の盲点です。クラウドストレージやVPNには注意を払っていても、USBメモリへの対策は「教育任せ」「自己責任」にされがちではないでしょうか。
企業にとってUSBメモリは、便利だが管理されていない情報経路です。今こそ、このデバイスに対して真剣に向き合い、使用状況を見直し、セキュリティレベルを底上げする時期に来ています。
USBメモリを狙ったサイバー攻撃が増加する背景
サイバー攻撃の焦点が、クラウドやネットワーク経由から物理デバイスへと再び移行しつつあるのをご存じでしょうか。中でも、USBメモリを用いた攻撃は年々増加傾向にあります。2022年以降、国家支援型のグループによるUSBメモリ経由の標的型攻撃が複数確認され、世界的に警戒が強まっています。
このような攻撃の増加には複数の背景が存在します。以下では、主な要因を3つの観点から整理します。
クラウド化の進展で物理的デバイスへの油断が増加
近年、多くの企業が業務をクラウド化し、オンラインでの情報共有が主流となりました。これにより、物理的なデータ持ち運びの必要性が減ったと捉えられ、USBメモリのセキュリティ対策が後回しにされる傾向が強まっています。
しかし現場では、一部資料をUSBメモリに保存して持ち出す、ネットワークに接続できない機器にファイルを移すといった場面が依然として存在します。たとえば、製造現場でのソフト更新や展示会での資料配布など、USBメモリは隙間を埋めるツールとして活用され続けています。
このように、クラウド化が進んでもUSBメモリの使用が継続している一方で、「すでに使われていないはず」という思い込みがセキュリティ体制の盲点を生んでいます。
ネットワーク非接続環境(エアギャップ)を狙う攻撃者の戦術変化
攻撃者は、インターネット経由での侵入が難しい環境に対し、エアギャップ環境へのアプローチを強めています。エアギャップとは、外部ネットワークと物理的に切り離されたシステムを指し、製造業、インフラ、軍事施設などで広く採用されています。
このような環境では、ネットワーク経由での感染が困難であるため、USBメモリなどの物理メディアが攻撃手段として用いられます。攻撃者は精巧に細工したUSBメモリを使い、対象者に接触させることで、閉じたネットワーク内部への侵入口を築こうとします。
特に懸念されるのが、内部関係者による意図しない協力です。たとえ善意で持ち込んだUSBメモリであっても、それが事前に感染していれば、企業内部からのマルウェア拡散につながる危険性があります。
マルウェア拡散・情報窃取におけるUSBメモリの静かで効果的な特性
USBメモリは、電源不要、OSによる自動認識、特別な権限なしでの使用が可能という点から、攻撃者にとって扱いやすい手段です。ユーザーの警戒をかいくぐりやすく、標的に気づかれないまま攻撃を進められます。
たとえば、USB接続と同時にマルウェアが自動実行されるよう設定されている場合、ファイルを開く前にすでに感染が始まっていることもあります。さらに、キーロガーや画面キャプチャツールを仕込むことで、ユーザーの操作を記録し、後日外部に送信することも可能です。
USBメモリが原因のセキュリティ事故
USBメモリは、その手軽さから多くの企業や組織で日常的に利用されています。しかし、その一方で重大なセキュリティ事故を引き起こすリスクを正しく認識している企業は、決して多くありません。
ここでは、実際に発生しているUSB関連のセキュリティ事故を、3つの類型に分けて解説します。
紛失や盗難による情報漏洩
最も発生頻度が高いのは、USBメモリの物理的な紛失や盗難による情報漏洩です。小型かつ軽量なため、通勤中や出張先、カフェなどでの置き忘れが後を絶ちません。とくに暗号化されていないUSBメモリであれば、第三者が簡単に中身を閲覧できてしまいます。
この種の事故が厄介なのは、物理的に発見されない限り、被害の有無を特定しにくい点です。情報が実際に流出したかどうかの証拠が残りにくく、対応の遅れにつながります。
従業員による不正なデータ持ち出し
USBメモリは、内部不正による情報持ち出しにも使われやすいツールです。
特に注意すべきは、退職予定者や職務に不満を抱える従業員など、明確な動機を持った人材の存在となります。業務資料や顧客リスト、設計図などを上司の目を盗んでUSBメモリにコピーするのは、技術的には容易です。
さらに深刻なのは、USBメモリへの書き出しログが残らないケースが多い点です。メール送信やクラウド利用にはログ管理があるものの、USBメモリ操作の詳細な記録を取得できている企業は限られています。
このようなリスクに対しては、USBメモリの使用制限や、書き込みを制限した専用USBメモリの導入など、不正を防ぐ予防的な仕組みの整備が求められます。
USBメモリを介したマルウェア感染
見落とされがちですが、USBメモリを媒介としたマルウェア感染も重大な脅威です。
この経路は、ファイル共有やクラウド上のやり取りと異なり、ユーザーの一操作で一気に感染が広がるスピードが特徴です。
たとえば、USBメモリに仕込まれたマルウェアがAutoRun機能を悪用し、接続と同時に不正プログラムを実行するケースが確認されています。こうした攻撃はウイルス対策ソフトをすり抜けることもあり、初期段階で気づきにくいという課題があります。
さらに、感染がネットワークを通じて自己拡散し、他の端末や共有フォルダに波及することもあります。
近年増加するUSBメモリを狙った攻撃手法
USBメモリを狙った攻撃は、単なるウイルス感染にとどまりません。攻撃者は、よりステルス性の高い手法や心理的なトリックを用いてターゲットに侵入し、長期的に情報を搾取する戦術を進化させています。
近年では、国家支援型グループや高度な技術を有するAPT(Advanced Persistent Threat)による、USBメモリを起点とした高度な攻撃が報告されています。以下に、代表的な3つの手法を紹介します。
「Living off the Land」戦術
「Living off the Land(LotL)」とは、感染先のOSやアプリケーションに標準で備わっている正規の機能を悪用する攻撃手法です。USBメモリを介してこの戦術が使われると、利用者に気づかれにくく、ウイルス対策ソフトでも検知されにくいという厄介な特徴があります。
たとえば、PowerShellなどのWindows機能を活用して、ネットワーク内の偵察やデータ転送を行うケースがあります。これにより、外部への通信を必要とせずに攻撃を進行できるため、EDR(エンドポイント検知・対応)を回避することも可能です。
USBメモリはあくまで侵入口に過ぎず、その後の攻撃はシステム内部の正規ツールを用いて行われます。これがLotLの厄介さであり、検知・遮断が困難な要因です。
サイレントレジデンシー
サイレントレジデンシーとは、USB経由で侵入したマルウェアが即座に活動を始めず、長期間潜伏する手法です。システム管理者やセキュリティ担当者の警戒が緩んだタイミングを見計らって攻撃を開始します。
この手法の問題点は、感染に気づかせないことにあります。
たとえば、USB経由で侵入したマルウェアが、PCの再起動や特定日時、特定アプリの起動をトリガーに作動するよう設定されていた場合、攻撃の発端を特定するのは困難です。
時間差攻撃によって、過去の操作や接続ログをたどっても明確な痕跡が残らないケースも多く、スパイ行為を目的とした長期的な潜伏に適しています。
ソーシャルエンジニアリング
技術的な攻撃だけでなく、人間の心理を突いたソーシャルエンジニアリングも、USBメモリを狙う手段として有効です。代表的な手法として、意図的に落とされたUSBメモリをターゲットが拾ってしまうケースがあります。
たとえば、「〇〇株式会社_人事評価2025」など、興味を引くファイル名を付けたUSBメモリを企業の出入口や駐車場に落としておけば、好奇心からPCに接続してしまう人が現れる可能性があります。このようなUSBメモリには、接続時に自動実行されるマルウェアや通信情報を盗み出すスクリプトが仕込まれていることが多く、たった一度の接続で感染が成立します。
ソーシャルエンジニアリングは、セキュリティツールでは防ぎきれないヒューマンエラーを突いてくるため、技術対策に加え、社員への教育や心理的対策が不可欠です。
USBメモリのセキュリティ対策4選
USBメモリは、その利便性の裏に多くのセキュリティリスクを抱えています。マルウェア感染や情報漏洩のリスクを軽減するには、技術的な対策と人的なルールの両面からの取り組みが欠かせません。ここでは、リソースの限られた企業でも現実的に実施可能な4つの基本対策を紹介します。
USBポリシーの制定と管理
まず最も重要なのは、USBメモリの利用ルールを明文化し、全社員が共通認識を持つことです。
会社支給または事前承認されたUSBメモリのみ使用を許可し、業務データの書き出しは必要最小限に制限。暗号化USBメモリの使用を義務化し、個人所有の機器接続は禁止する。また、使用ログを自動的に取得・保管する仕組みも整備する必要があります。
さらに、デバイス制御ツールを導入し、利用権限を部署や役職単位で管理すれば、リスクはさらに抑えられます。
USBスキャン・監視ツールの導入
次に、USBメモリは持ち込み型の未知の脅威と捉えるべきです。
接続と同時にウイルススキャンを強制実行するソフト、接続履歴をリアルタイムで監視するツール、認可されたUSBメモリ以外の接続を自動でブロックする仕組みを活用することで、感染を未然に防ぐと同時に、トラブル時の調査も迅速になります。
AutoRun機能の無効化とOS設定の強化
マルウェアの多くが悪用するAutoRun機能の無効化も不可欠です。
WindowsがUSBメモリ内のautorun.infを検出して自動でプログラムを実行するこの機能は、攻撃の引き金となり得ます。グループポリシーやレジストリ設定での無効化、USBメモリを読み取り専用に制限する設定、管理者以外の利用制限などを講じることで、リスクを大幅に軽減できます。
社員・現場担当者への教育
技術的対策を支えるのは従業員の行動です。USBメモリを拾っても使用しない、挿入前に必ず上司に確認する、自宅用と業務用を区別する、といった基本行動の徹底が重要です。
定期的なeラーニングや研修を通じて、被害事例を交えながら知識を行動に変える教育を実施して、ヒューマンエラーを防ぐ土台を築きましょう。
定期的なパッチ適用・脆弱性管理
USB経由の攻撃はOSやソフトの既知の脆弱性を突いてくるため、システムを最新の状態に保つ体制も必要です。
OSやウイルス対策ソフトのアップデートを自動化し、IT資産を一元管理してパッチ未適用端末を可視化することが、USBメモリ対策の前提条件といえます。USBメモリ対策は単独で完結するものではなく、組織全体のセキュリティ体制と密接に関わるテーマなのです。
USBメモリは安全という盲点がセキュリティ危機を招く
USBメモリは手軽な反面、個人判断で自由に使われがちです。
接続ログが残らず、接続や取り外しも見過ごされやすいため、管理が甘くなりやすいのが実情です。この隙を攻撃者は突いてきます。まず、「USBメモリは安全」という思い込みを捨て、リスクを前提とした管理体制を整える必要があります。
さらに、現代のサイバー攻撃は完全には防げません。
重要なのは、被害を前提に備え、影響を最小限に抑えることです。USBメモリを通じた情報漏洩やマルウェア感染は、社内にとどまらず、ダークウェブでの情報売買など深刻な事態につながりかねません。
ダークウェブ監視サービスは、組織名やメール、ドメイン、取引先情報などに関連するデータの不正流通を常時監視し、漏洩の兆候を早期に検知します。これにより、深刻化前の対応が可能です。貴社情報がすでに流出している可能性もあります。まずは無料トライアルで、状況をご確認ください。